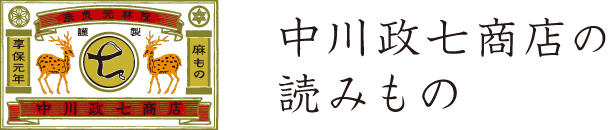日本人が知ってるようで知らないかつお節。最高級の土佐「本枯節」ができるまで
エリア
日本食に欠かすことのできない「旨味」。甘味、塩味、酸味、苦味に次ぐこの第五の味覚は、近年「UMAMI」として海外でも認知されつつある。その旨味に欠かすことのできない「出汁」のひとつが鰹節(かつおぶし)だ。日本人の食生活に染み込んだ鰹節。
しかし、その鰹節がどうやってできているのか?どんな種類があるのか?僕たち日本人は実はあまり知らない。
今回は、高知県・土佐市の漁師町である「宇佐町」の鰹節工場、「竹内商店」に足を運び、日本人として知っておきたい鰹節のつくり方、そして親子三人で家業を紡いでいくことについて聞いてきた。

高知市内から南に車を走らせること30分。かつて鰹節製造業が発展した宇佐町は、江戸時代より受け継がれる「土佐節」発祥の地といわれている。幕府への献上品として納められるほどの品質を誇った宇佐町の土佐節だが、機械を導入した効率の良い製造を用いた製法の台頭により、いまでは製造する工場も激減してしまった。
そんななか、三代に渡って土佐節を守り続けているのが竹内商店だ。
意外と知らない鰹節の種類。最高級の「本枯節」
鰹節には大きく分けて「荒節(あらぶし)」と「枯節(かれぶし)」があり(*1)、製造法や製造期間が異なる。
荒節(「新節」とも呼ぶ)は製造期間が20日前後と生産効率もよく、スーパーなどで販売されている鰹節の約80%がこの荒節を削ったもの。対して枯節は、荒節の状態からカビ付けと天日干しを行ない、水分を取り除いたもの。完成までなんと数ヶ月を要する。
*1:直火した柔らかい生節(なまりぶし)などもある
枯節からさらにカビ付け・天日干しを何度も繰り返したのが「本枯節」だ。旨味をさらに凝縮した本枯節は、高級料亭などでも使用される最高級の鰹節。出来上がるまでにおおよそ4ヶ月、昔ながらの製法なら半年ほどかかることから、現在では本枯節の生産は全国の鰹節生産のうち、わずか数%ほどとなっている。
竹内商店は昔ながらの土佐製法で本枯節を製造する数少ない鰹節工場だ。高品質な本枯節は農林水産大臣賞など数々の賞を受賞している。この日は、お父さんとお兄さんとともに、家族三人で竹内商店を営む竹内仁了(じんりょう)さんに工場を案内していただいた。
竹内商店が守り続ける、土佐・本枯節ができるまで
朝から工場を伺ってすぐに気づくのが、建物の外にも広がる芳ばしい鰹の香り。作業場ではお母さんたちが黙々と作業をこなし、鰹を煮る年季の入った釜から立ち上る蒸気が、朝の空気と交わる。なんともいえない清々しさは、昔ながらの「日本の食卓」を思い起こさせてくれる。



竹内さんがまず案内してくれたのは、鰹が保存されている冷凍庫。冷凍庫には所狭しと、小ぶり、大ぶりな鰹が冷凍保存されている。
「小ぶりな鰹と本枯節(ほんかれぶし)用の鰹とでは、大人と子供くらい違いますよ。本枯節には5〜6kgくらいの大きい鰹を使います」と竹内さん。
これだけの数の鰹たちに見つめられることもなかなかないので、少し異世界に来たような気持ちになる。

生切り
鰹節の工程は大きく、鰹をおろす「生切り(なまぎり)」、一気に煮る「釜立て(かまだて)」、燻す「焙乾(ばいかん)」、さらに水分を飛ばし旨味を凝縮する「カビ付け」の作業に分けられる。
まず半日ほどかけて水で解凍された鰹の頭を切り落とし、内臓をとり除いて水洗いした後に3枚におろす。
この生切り工程で切り分けられた鰹の部位は、ほとんどが余すことなく使われるのだそう。
「鰹って捨てるところが本当に少ないんですよ。心臓は「ちちこ」という高知の珍味になりますし、内臓は酒盗にも使う。売り物ではありませんが、余った一部の部位も細かく粉砕してうちで出汁に使っています」
釜立て
生切りが終わると、「煮籠(にかご)」と呼ばれる網かごに鰹を並べ、釜で約1時間半ほど煮る。この「釜立て(かまだて)」と呼ばれる工程で、鰹節のベースとなる味が決まるのだそう。煮る温度が高すぎると身が割れ、低すぎると生臭くなり夏場は不良品となるため、ここでも繊細な調整が必要になる。

意外なことに、美味しい鰹節には脂のたっぷり乗った鰹よりも、脂が少なく淡白なもののほうが向いているのだという。
「日本近海で取れる鰹、特に初鰹(はつがつお)は、鰹節にうってつけなんです」
「初鰹(はつがつお)」とは、4〜6月ごろに餌を求めて北上する鰹のこと。赤身が多くあっさりとした初鰹を使った鰹節は、「初鰹節」と呼ばれ、最も品質が高いとされてる。(*2)
*2:9月頃から南下し始め、より栄養を摂取して脂の層がたっぷり乗った「戻り鰹」は刺身として好まれる

また竹内商店の鰹節は網や「一本釣り」で捕獲された鰹を使う。一本釣りで獲った鰹は、網で水揚げしたものと比べ鮮度が良く、脂がそこまで乗らず淡白で形も良いので、鰹節にするのはベストなのだそうだ。

バラ抜き

煮上がった鰹を釜から上げると、「バラ抜き」という骨を抜く工程に入る。長く勤めるベテランの職人さんたちが、見事な手際良さで次々と骨を取り除いていく。
バラ抜きは形のよい鰹節を作るのに重要な作業。形の美しいものが、もちろん品質の良い鰹節と評価される。
「美しい形っていうのは、日々追求ですね。正直に言うとセオリーはないです。お手本とされる形はありますが、作る人それぞれに美しさの基準があるので、一概には言えません。みんな、自分たちが作るものが一番美しいと思っています。ただ、僕は普通の焼き魚も骨を取り分けるのが苦手なので、熟練の技にいつも驚かされますね(笑)」
焙乾
次にいよいよ鰹を燻していく。焚納屋(たきなや)と呼ばれる焙炉に鰹を入れ、薪を焚いてどんどん燻していく。これを「焙乾(ばいかん)」と呼ぶそうだ。




竹内商店の焙乾が特徴的なのは、手火山(てびやま)式と呼ばれる方法で鰹が燻されていること。
手火山式は、主流である焙乾効率のいい焼津式乾燥機と異なり、下から薪を焚いて上の階まで何層にも分け、少しずつ火から遠ざけながら燻す。時間もかかるうえに、雨の日などの湿気にも影響を受ける。何千という鰹を積んだ鉄のかごを上に運ぶのも一苦労だ。
しかし竹内商店は先々代から続く、この昔ながらの方式を守り続けている。
その日の気温や湿度、薪の乾燥具合、魚の大きさや脂肪分の量、燻製された鰹の皮に表れるわずかな差異は、熟練の職人の判断によってしか見分けられない。
「効率化しようと思えばいくらでもできるんですが、それをやってしまうと、それなりのものしかできない。そこは変えられないこだわりというか。工程的にも、少しずつ水分を飛ばす焙乾が一番の味の決め手ですから」



焙乾を終えた鰹は片手で持てるくらいのサイズまで小さくなり、ここでようやく鰹は鰹節にに変わる。
「焙乾で鰹の大体の水分を抜き、水分量は30%程度まで少なくなります。この焙乾が終わった状態の鰹節が『荒節』になります。焙乾が2〜3日程度の荒節もあって、そのままの状態か、表面のタールを落として市場に出ます。これを削ったものが、市場に出ている『花かつお』になるんですよ」
そこから脂の量やサイズを見極め、本枯節に適していると判断された鰹節はそこからさらに「カビ付け」の工程に進む。

「脂が乗ってないもの、より淡白なものを、色味や焼け方、音や硬さで判断します。ほら、皮のこことここがちょっと違うでしょう?」
と言われたものの…やはり素人目には判別はかなり難しい。
カビ付け
表面のタールをとり除き、カビ菌を吹きかけた鰹節は、カビ付け庫に保管される。カビ付けの工程は、全体にカビが行き渡るまでに約3〜4週間ほど、天日干しも含めると2ヶ月ほどの時間を要する。
「カビ付け工程でカビ菌を吹きかけるのは1回で、そこからカビを培養して、干してという工程を繰り返すんですよ」
培養と天日干しを繰り返し、時間をかけて干すことで、カビが鰹の芯まで水分吸い取ってくれるのだそう。最終的には鰹節の水分量は15〜20%まで落とされる。
「急激に乾燥させてしまうと、カビの根が鰹の芯まで入っていけなくなるんです。表面だけが乾燥してしまって、水分が抜けきれずウェットな鰹節ができてしまう。
飴と鞭じゃないけど、日乾してカラカラになったカビがまた鰹節の水分を吸い上げてくれるんです。ギリギリまで水分を抜くので、出来上がった鰹節は高タンパクですごくヘルシーなんですよ」
素朴な疑問として、「カビ」を使うのになぜ体には悪影響がないのかということ。
「カビはカビでも、置いてあったパンにできるカビなどとは種類が違うんです」と竹内さん。カビの食材というのはほかにチーズなどがあるが、それと一緒で、食べても害のないカビなのだそう。

こうして、全体で4〜6ヶ月、手間暇をかけた丹念な作業のすえに、旨味の凝縮された最高級の本枯節が出来上がる。本枯節は最初の鰹からは信じられないほどに硬くなり、鰹節同士で叩けば「カンカン」と甲高い音が鳴る。


削り

出来上がった本枯節を鉋(かんな)で削ると鰹の香りがぶわっと立ち込め、鰹を薄く削った断面は、宝石のような光沢を放っている。


薄く削ったあとの本枯節の断面は、魚とは思えないツヤが出る
薄く透けた橙色の削り節は、口に入れるとこれまで味わったことのないコクと旨味が広がる。
本枯節はタールをとった後にカビ付けをするので、コクがあってかつ雑味のない、すっきりとした出汁が取れるのだそう。逆にタールを残している荒節を削って取った出汁は、濃くてインパクトのある出汁が取れる。

「美味しいでしょう?やはり、削りたてのものは風味が格別です。これに食べ慣れている人はこの美味しさを知っているので、逆に削ってあるものは食べられなくなりますよ。ぜひ、宇佐町の土佐節、味わっていただきたいです」
この仕事をやっていてよかったこと。「子供を二人を育て上げられたことかなぁ」

鰹の仕入れ値が時代とともに上がる中で、売値はあまり変わらず儲けられないため、手間のかかる昔ながらの製法で鰹節を作る生産者は激減してしまった。
日本の伝統的な産業においては珍しいことでもないが、そんな状況の中で竹内商店は、仁了さん、太一さんの兄弟がお父さんの昌作さんからバトンタッチを受けて親子三人で切り盛りしている。太一さんは東京の大学の理工学部を卒業し、某王手メーカーの経理を7年間経験して竹内商店へ。仁了さんは水産学部とマグロの解体屋や鰹の選別師の修行を経て竹内商店の家業を継いだ。
仁良さんは竹内商店を継ぐために水産のノウハウを培い、「兄弟で同じことしても意味がないかなと思って」という太一さんは、仁良さんとは異なる経験を積み重ね、それぞれが現在の家業の経営に生かしている。二人はお互いのことを話すときは少し照れ臭そうにしながらも、
「小さい頃から、なんだかんだで継がなきゃとは思ってたかなぁ」と、お父さんが残してきたこの竹内商店について口を揃える。
しかし、大学進学の頃には家業を継ぐことをな内心決めていたという仁了さんは、「特に親から継げと言われたことはなかった」という。
「なんででしょうねえ。続けていれば、誰かしらが分かってくれるから続けているというのもあるし。一番の理由は単純に好きだから、美味しいからですね(笑)。子供の頃からずっと食べているし。辞めたらこの美味しいものが実家に帰っても食べられなくなっちゃうのかぁと。それが嫌だったんですね」と仁了さん。
職人の仕事や地方の伝統的な産業を若者が継がないというケースが多い中で、二人の息子が高知に戻り家業を継いだことを、「うーん、へへへへ」と、お父さんの昌作さんは黙々と鰹節を削りながら照れ臭そうに話す。

「(継いでほしいという気持ちは)まぁ、あったけどね。自分がね、幸せにならないといけないことからね、自分が好きなことをやるのが一番だからね。この産業だって問題は多いから」
「若い人には分からんかもだけど、団塊の世代は金の卵ともてはやされて産業的にも勢いのある時代だった。でも今はその時代とは全然違うから、継げとは簡単には言えん。今は簡単にOEMって簡単に自分のところの商品にして売ったり、いろいろやり方があるけど、うちらの商売はそれができないからねえ。それが辛いところやけど。でも、うちのものを原料にいろんなものを作るのは私には無理やから、息子たちがやりたいならね。若い人の考えで」
寡黙なお父さんについて、息子の二人は「何も教えてくれない」とも。
「自分らも父親には何も教えてくれなかったからねえ。自分がある日突然パタッといなくなった時に、『あれはどうやってた?』では困るじゃない。だからどんどん自分でやって、『これはどうする?』って時にはちゃんと教える。学校の勉強だって、先生が教えるのを聞いているだけで頭が良くなるほど、教育は簡単なものじゃない。それと同じようなことで、自分で感じて疑問を持たないといいものはできないからね。背中を見て学べ、っていうほどかっこいいものではないけどね。この仕事をやっててよかったこと…やっぱり、子供を3人育て上げられたってことでしょうね」
知ってるようで知らない鰹節の世界。日本食に不可欠な出汁の文化は、竹内さんたちのような職人さんたちにこうして支えられていた。慣れ親しみすぎてあまり深く考えることのなかった日本の食材も、ちょっと知るだけで、いつもの味噌汁が、煮物が、少し優しい味に感じるかもしれない。

<取材協力>
竹内商店
〒781-1163 高知県土佐市宇佐町福島2824−3
088-856-0129
取材・文:和田拓也
写真:uehara mitsugu